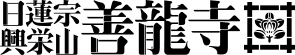今の法華経の文字は皆、生身の仏なり。我等は肉眼なれば文字と見みるなり。たとへば餓鬼は恒河を火と見る、人は水と見、天人は甘露と見る。
水は一なれども、果報にしたがつて、見るところ格別なり。
この法華経の文字は、盲目の者はこれを見ず。肉眼は黒色と見る。二乗は虚空と見、菩薩は種種の色と見、仏種純熟せる人は、仏と見たて奉。
日蓮聖人『法蓮鈔』より
【現代語訳】
法華経の文字は、一字一字がみな生きた仏であるが、しかし我等凡夫の肉眼には、ただの文字としか見えない。
たとえば、餓鬼にはガンジス河(恒河)の水が火に見え、人には水に見え、天人には甘露に見える。同じ水でも、見る者がそれぞれうけている境遇の違いによってそれぞれ別の物に見えるのである。
この法華経の文字は、盲人には全然見えないが、凡夫の肉眼では黒色の文字に見え、声聞・縁覚の二乗の慧眼では空に見え、菩薩の法眼では種々の法門に見え、「仏に成る種の熟した仏眼を持った人」は、この文字を仏と見奉るのである。(『法蓮鈔』より)
当山では「如法写経会」という『法華経』写経の会を開いていますが、写経の修行では「お経典の一字を書くことは一仏を刻むこと」だと教えています。「一字三礼」といって、正式な写経行では一字書くごとに三回その「文字=仏さま」を礼拝することを勧めています。
しかし、文字がそのまま仏さま、といわれても素直にそうだとは思えないのが、私たちの実感でしょう。経典とはいえ、なぜ「文字」が「仏さま」なのでしょうか? 冒頭の日蓮聖人のお言葉は、そうした私たちの疑問をやさしく解いてくれます。
まずは、物事の見え方は境遇によって随分と違うということです。それを、十に分けて心の在り方を説明した十界(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天・声聞・縁覚・菩薩・仏)を使って説明しています。地獄~天までは輪廻する「六道(ろくどう)」の境遇ですが、声聞~仏までは「四聖(ししょう)」の境地になります。つまり二乗からは、その修行の境地で見え方が違ってきます。
人が「黒い文字」にしか見えないものを、二乗(声聞と縁覚)は「空の教え」、菩薩は「多くの法門」、そして仏の眼を持った者は「生きた仏」と見るのです。この仏眼の境地に至ったからこそ、文字が仏に見えるのでしょう。ですから、黒い文字が実は生きた仏だと実感するためには、いかに黒い文字を「読み解くか」が最も重要な修行になってきます。
「読む」という行為も決して一様ではありません。日蓮聖人は、『法華経』を読むのに目や心で読むだけでなく、「自らの身に当たって読む」という色読を、最高の読み方とされました。色読というのは、身に当たって体験的に読むということです。
『法華経』には、「この教えを弘める者は法難に遭(あ)う」と説かれています。日蓮聖人は、多くの法難体験によって『法華経』を身に読んだと述べられて、自ら「法華経の行者」と名乗られました。色読とは、つまり信仰的で殉教的な読み方といえるでしょう。その読み方は、『法華経』の文字を解釈するのではなく、『法華経』の文字を生きるということです。
また、日蓮聖人は『祈祷抄』という御遺文において「此の経(法華経)の文字は、すなわち釈迦如来の御魂なり」と述べておられます。
御悟りをば法華経と説きをかせ給へば、此の経(法華経)の文字は、すなわち釈迦如来の御魂なり。
一々の文字は仏の御魂なれば、此の経を行ぜん人をば釈迦如来、我が御眼の如くまほり給うべし。
『祈祷抄』
お釈迦様のお悟りの全てが説かれている『法華経』であればこそ、その経文の一字一字にはお釈迦さまの御声が、御魂が宿っているのです。その御魂は、身をもって此の経を行じること、つまり『法華経』の文字を生きることで見えてくるのです。
日蓮聖人は、蒙古襲来を目前にして「仏眼をかつて、時機をかんがへよ。仏日を用て、国をてらせ」(『撰時抄』)と人々に警告を発しました。文字を仏と見ることのできる仏眼とは、すべてを見通しての時代を読む「悟りの眼」に他なりません。しかし、そうした仏眼とは、日蓮聖人のような色読によってだけではなく、心身ともに仏を礼拝する「一字三礼」の写経行によっても、徐々に近づくことのできる境地ではないでしょうか。
『法華経』の方便品には「小善成仏」が説かれています。小善成仏とは、『法華経』を讃えるどんな小さな善根であっても仏になる種(仏種)を育てて、やがて悟りに至ることができるという法門です。一字を書くことが一仏を刻むことに等しいという写経の功徳は、徐々に自らの仏の種を育てて、やがて「仏種純熟せる人」となって、「(文字を)仏と見奉る」境地へと導いてくれるでしょう。
毎日のニュースに接しても、大きく時代が動いていることが実感される昨今です。皆さまどうぞ、小善を積むことで身と心を調えて、水のような穏やかで絶えることのない信心をもって、日々の暮らしを感謝と反省で充実させながら、年末年始を元気にお過ごし下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
合 掌